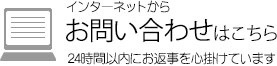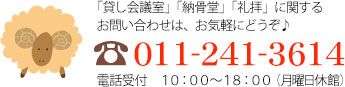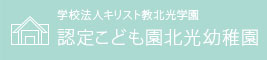札幌 納骨堂 札幌市中央区 貸し会議室 納骨堂/クリプト北光
日本基督教団 札幌北光教会 日曜礼拝 木曜礼拝 牧師/指方信平、指方愛子


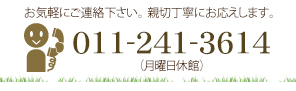
>札幌北光教会/トップ >牧師紹介・説教 >パウロの弁明と良心
- テーマ
- 「パウロの弁明と良心」
- 更新日:2025年7月22日
- 2025年7月13日 聖霊降臨節 第6主日 説教要旨
使徒言行録 24章1節〜27節 - 牧師:指方 信平
◆終わりの裁きへの「希望」
使徒言行録24章は、ユダヤ総督フェリクスに対する大祭司アナニアの告発と、それに対するパウロの弁明です。大祭司の弁護士テルティロは、パウロのことを「疫病のような人間」「ナザレ人の分派の首謀者」などと数々の激しい言葉で訴えました。これに対しパウロには弁護士はついていません。いわば「聖霊」という弁護者が彼に語るべき言葉を語らせていると言えるでしょう。その言葉は告発者たちを罵るような言葉ではなく、事柄を正確に語り、説得力のある弁明です。パウロは、告発者たちが何ひとつ正当な理由や証拠のないままに訴えていると指摘しました。先の最高法院での「死者の復活の希望」についての発言も、それ自体が訴えの理由にはならないはずだ、と。弁明の中でパウロは言いました。「正しい者も正しくない者もやがて復活するという希望を、神に対して抱いています」(15節)。正しい者も正しくない者もやがて復活するとは、やがて神の前で最後の審判を受けるために一度すべての人が復活する、という意味です(使徒信条:生ける者と死ねる者とを裁き給わん)。ここでパウロは、ユダヤの最高法院やローマの法廷という人間の裁きではなく、終わりの日の神の裁きというものを見つめているのです。そして、パウロにとってその裁きは「希望」でした。神の最終的な裁きが、「滅び」ではなく、「救い」「命」への裁きであると知っているが故にそれは希望なのです。
パウロという人は、人間が神の前にいかに罪ある存在かということを深く見つめた人です。創り主である神の御心にどうしても背いてしまう、「原罪」と言わざるを得ないような人間の破れと欠けに満ちた有様を見つめました。それゆえ本来ならば、神の前にただただ滅ぼされるほか無いような自分が、しかし、神の限りない愛と忍耐によって、キリストの十字架の死と復活の命に結び合わされ、神の子として新たに、とこしえに生きる者とされているのだという恵みを知るに至りました。このキリストという恵みのゆえに、パウロは希望を抱くことができたのです。この希望に支えられてこれまで歩み、そして今この不当な訴えに対しても、絶望ではなく、むしろ一層鮮明にキリストの死に自分が結ばれ、キリストの復活の命に自分が生かされていることを自覚させられ、まことの強さを持って臨んでいるのです。
◆パウロの良心
「私は、神に対しても人に対しても、責められることのない良心を絶えず保つように努めています。」
一般的に良心とは、物事の是非を、目先の損得・利害というものに左右されず、自分の内にある価値観に基づき、己の良いと信じるところに従って行動する気持ちです。しかしパウロの良心とは、自分がどこまでも神に赦され、子として愛されたという恵みを見つめ、この恵みに応える生き方を選び取ろうとする気持ちです。何が神の恵みに応える在り方か、福音を恥としない在り方か、神の喜ばれることかを求める在り方です。その信仰的良心が、パウロをこの場で立たせているのです。総督フェリクスには、パウロから賄賂を受け取ろうとする下心があり、パウロの語る耳の痛い話(正義と節制と来るべき裁きについて)を避けるという態度に終始しました。また後任の総督となったフェストゥスはユダヤ人から気に入られようとしてパウロを監禁したままにしておきました。使徒言行録は、神の前に良心を持って語ったパウロと、権力や富に恋々とする権力者を対比的に描いています。
◆限りなく赦され愛された者の良心
円山墓地でポーリン・レーン、ハロルド・レーン夫妻の墓前礼拝を行いました。夫妻は真珠湾攻撃が実行されたその朝にスパイ容疑で不当逮捕、拘留され、裁判では有罪判決が下されました。大通拘置所、苗穂刑務所に送られ、その後、最後の日米交換船でアメリカへと送還されました。夫のハロルドは、第1次大戦で良心的兵役拒否を貫いた人です。信仰的良心をもって「汝殺すなかれ」を守り、クエーカーのキリスト者として、常に良き隣人・友として生きることに生涯をささげようとした良心の人です。スパイとして有罪とされるなど全く不当で愚かな裁判、戦争がもたらした悲劇でした。1951年に夫婦は札幌へと戻ってこられましたが、そこで夫妻から弁解や弁明を聞いたという人はいません。ただただポーリンは病気で倒れる時まで北光教会の役員として、教会を愛し、北大を愛し、故郷札幌を愛することに生き、74年のその生涯を終え、円山の地で眠りに就きました。そこにレーン夫妻の証があります。戦後80年を迎えます。戦争へと再び向かいつつあるような時代の中にあって、私たちはどこに立つのか。神に限りなく赦され、愛されてあるという恵みに立って考え、語り、行動する良心を絶えず保つよう努めたいと願います。
⇒ 前のページに戻る