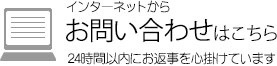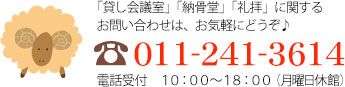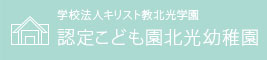�D�y �[���� �D�y�s������ �݂���c�� �[����/�N���v�g�k��
���{����c �D�y�k������ ���j��q �ؗj��q �q�t/�w���M���A�w�����q


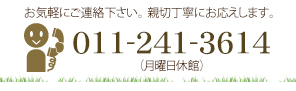
>�D�y�k������/�g�b�v�@ >�q�t�Љ�E�����@ >������̈�
- �e�[�}
- �u������̈��v
- �X�V���F2025�N6��2��
- 2025�N5��25���@������ ��6����@�����v�|
�e�T���j�P�̐M�k�ւ̎莆�T�@3��11�߁`13�� - ���͖q�t�F��q ��Y
1. �p�E���́u���݂��ւ̈��Ƃ��ׂĂ̐l�ւ̈��v�i�R�F12�j�ƌ����B�p�E�����p�����u���v�Ƃ����P��̓M���V����Łu�A�K�y�[�������Łv�ŁA�_���l�Ԃ�����Ă����������Ƃ����Ӗ��ł���B�p�E���͐l�ԓ��m���܂��A�_�̈��ɕ���Ĉ�����悤�ɂƑ����B�p�E���́A���̈����A�悸�u���݂��v���m�Ŏ��s����ƌ����B�u���݂��v�Ƃ͂��̎莆�ł̓e�T���j�P����̒��ԓ��m�ł���B���ꂩ��p�E���́A�u�S�Ă̐l�X�Ɂv�����s���Ƒ����B����̒��ԂƋ�ʂ��āu���ׂĂ̐l�X�v�ƌ����̂�����A�e�T���j�P����̊O���̐l�X���w���Ă���B�������āA�p�E���́A����̒��ԂƂ��̊O���̐l�X�Ƃ���������O��Ɉ��̎��s�𑣂����B����A�p�E���͋����̂́u�A���i�A�C�f���e�B�e�B�j�v���ӎ����āA�L���X�g�҂Ɉ��̎��s��������B
�Q�D�����̂̋A�����Ⴄ���Ƃň��̎��s���قȂ�ƃp�E���͌����̂��B���̖₢�����͂���̌�����l��������ꂽ�B���ĕ��C�������鋳��Łu�����̉�v���������B���̋���⑼����̃����o�[���ꏏ�Ɋw�B������̕��̒a�������ԋ߂��������A�������̋���̃����o�[���A�u�搶�A���̕��̂��߂ɂ��F�肵�Ă��������v�Ɗ��ꂽ�B���͊��ŋF�����B�W���A���̕����A�����͑�����̃����o�[�Ȃ̂ɐ搶�͂��F�肷��̂ł��˂ƌ���ꂽ�B���̕��̋���ł́A�q�t�������̋�����ȊO�̐l�̒a�����̏j�����F�邱�Ƃ͂Ȃ������������B����̏������Ⴄ�ƒa���j�����F��Ȃ��H���ɂ͋̒ʂ�Ȃ������u�ĂɎv���Ĉ�a�����c�����B����A�����ł͂Ȃ��B��q�̍l���̕����Ԉ���Ă���B������̒����Ƃ��ċF��ł������u�Ă͓��R�Ȃ̂��B���ꂪ�p�E���̌���������s����̓I�ȗ��V�Ȃ̂��낤���B
�R. �������̖₢�͂�������n�܂�B�����āA�����Ŏ������͗����~�܂��čl�������B�Ȃ��Ȃ�A�C�G�X�̌��s�ɏƂ点�A�p�E���̌��t�͂����Ɛ[��������Ƃ߂�ׂ����t���ƋC�Â����炾�B�p�E�����g���u�M�Ɗ�]�ƈ��A���̂����Ƃ��傢�Ȃ���͈̂��i�A�K�y�[�j�v�i�R�����g�T13�F13�j�ƌ��B���́u�����Ƃ��傢�Ȃ鈤�v�Ƃ����m�M�ɂ����Ă����A���O�҂ɑ���u������̈��v�̐[���Ӗ����������͒m��B�_�̎͂��Ƃ��Ď����ꂽ�u�傢�Ȃ鈤�v�A����́A����������A�C�G�X���p�E���̗אl�ƂȂ��Ă������������ƂɌ��ꂽ�_�̈����B���̃C�G�X�ɂ�����_�̈��ɉ������т��p�E���̏،����B�����������l���B�p�E����߂����_�̈��ɕ���āA�N���̗אl�ł��낤�Ƃ���A�ڂ̑O�̌����ɑ����������Ƃ��Đ悸�߂��l�X����n�߂邱�Ƃ͂���B�������A�_�����g�͂����ɗ��܂�Ȃ��B�ނ���A���̈Ⴂ���z���閳���̈��������Ď��������B�C�G�X�������ł������悤�ɁA�_�̈��͐l�Ԃ̍��o���l�X�ȕ����u�Ă��z���Ă����אl���A���l�����߂�אl���ɑ��Ȃ�Ȃ��B
�S. ���������g�̋A�����v���Ԃ��Ă݂悤�B�������͗l�X�ȋA���������Ă���B����A�@���A�Ƒ��A��ЁA�w�Z�A�s���A�����ȂǁB�N��������̋A���ɂȂ����Đ����Ă���B�����������X�̋A��������Đ����鎄�����̐l���ɁA�_�̈��͕����u�ĂȂ��K���B�����āA�����̎͂��Ƃ��āA��������_�Ɍ��э��킹��B������A�������͐_�̈����̈����ƌ������Ȃ��B�����ł���A�������̈����_�ɕ키���ł������قǁA���̈��́A�l�X�ȋA���̈Ⴂ���z��������͂ƂȂ��Ď������𑣂����ƂɋC�Â��B������A�_�̈��ɂ͍��ʂ��������ޗ]�n�ȂǁA�ǂ��ɂ��Ȃ����Ƃ𗝉����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�_�͐l�Ԃ��A���̈Ⴂ�ɂ���āA�����邱�Ƃ�ɂ��ނ悤�Ȃ����L���_�ł͂Ȃ��B
�T. �אl���݂̍�����l����������b������B�I�N�X�t�H�[�h��w�̋����Ńm�[�x���o�ϊw�܂����A�}���e�B�A�E�Z���̋L�������b���B�Z���͌��݂̃o���O���f�V�����a���_�b�J�̏o�g�B1943�N�A�_�b�J�̊X�p�ŃC�X�������k�̃J�f���E�~�A�Ƃ����j��������D��ꂽ�B����������ɂ߂��q���Y�[���k�Ƃ̏@���Η��Ɋ������܂ꂽ�̂��B���ƒ��̃J�f���E�~�A�͓�������T���ĕ����܂�邤���ɁA�q���Y�[���k�n��ɖ������B�����Ŗ\�k�̏P�����A�m���̏d�����āA�ꌬ�̉Ƃ̒�ɓ������B�����炯�̃~�A�ɋC�Â����̂͂��̉Ƃ̏��N�������B���N�̓~�A���\�k�ɒǂ��ē������̂��ƋC�Â����B�������A���͂�Ȃ��p���Ȃ��A�~�A�͏��N�̘r�̒��ő��₦���B
�U. ���̏��N�Ƃ�10�̃A�}���e�B�A�E�Z���������B�Z���͂��̐��S�ȋL����Y�ꂸ�A65�N��A�~�A�̎��ɗ���������̌���ނ̖{�ɋL�����B���̖{�̒��ŃZ���̓~�A��P�ɏ@���Η��̋]���҂ƌ��Ă͂��Ȃ��B�����ɃZ���̑��҂ւ̑z���͂̐[�����M����B�Z���͏����Ă���B10�̎��ɂ͉����ł��Ȃ������B�~�A�̓C�X�������k�Ƃ��ĎE���ꂽ�Ƃ������邪�A�Ƒ��̂��߂Ɏd�������߂ĕ����Ȃ���A�n�����J���҂Ƃ��ĎE���ꂽ�Ƃ�������B���N�Z�����ڌ������̂́A�C�X�������k�ł��邾���łȂ��A�J���҂ŁA�v�ŁA���e�ŁA�n�����K�w�̖��O�̃J�f���E�~�A�������B�m���Ȃ��Ƃ̓J�f���E�~�A�������I�ȋA�����Ă������Ƃ��B���̂��Ƃɑz���͂��y�ׂA�l�ԑ��݂̑��l�ȉ��[�����A�����ĎE���ꂽ��l�̐l�Ԃ������A���̐l�ԑ��݂̏d�����������̐S�ɔ����Ă���B
�V. �Z�����g�̓C�X�������k�̉ƒ�ɐ��܂������B�������A�����̓C�X�������k�ł͂Ȃ��A���_�_�҂��Ƃ����B�܂��Z���̕��̓_�b�J��w�̋����Ōb�܂ꂽ�K�w�������B�����̓_�ł̓Z���́A�~�A�Ƃ͂��Ȃ�قȂ����A�������l���B����ɂ�������炸�A�Z���́A�����I�ȏ���قȂ鑼�҂̗��s�s�Ȏ���Y��邱�Ƃ��Ȃ������B�܂��A�ɍ��̎v���������Ă�����L�����B������̏@���ɂ��A�������A�_��M���Ȃ��Ƃ����Z���B���̐l�́A�l�Ԃ��Ȏ҂Ƃ��Č��ߋL�����������p�ɁA���͐_�ɕ키���̐S��������B�Ђ邪�����āA�C�G�X�E�L���X�g�̐_�ɂ���āA���邪�܂܂̎������͂��̒��Ɏ�����A�_�̈��ɉ����Đ����Ă���͂��̎��B�L���X�g�҂����F���鎄�́A�͂����Ăǂ����Ǝ��₹���ɂ͂����Ȃ��B
�W. �u�����邱�Ƃ����Ȃ��ŏ@���ɂ��Č��l�����܂��B�����킩���Ă��Ȃ��̂ł��v�ƌ�����l������B�}�U�[�E�e���T���ޏ����g���܂߂ĐM�̗L��������ߒ��������t���B�}�U�[�͑��l�ȋA���̐l�X���s�������C���h�E�R���J�^�ɐ��U���߂������B�}�U�[�͍s���|��Ď���҂l�̉Ɓu�j���}���E�J���_�C�v��n�݂����B�����Ɉ�l�̘V�l�����̑��ŒS�����܂ꂽ�B���͂⎀��҂����̏�Ԃ������B�}�U�[�́A���̐l�̐g�̂�A�Ō�̊�]��q�˂��B���̐l�́u���̓q���Y�[���k�ŁA���̑m���K���̃o�������ł��B�o�������m�Ƃ��Ď����}�������v�Ɠ������B�}�U�[�̓o�������o�T��T���āA������J���A���̐l�������}����܂Ńq���Y�[�̋F������̐l�̖��ӂŏ������B�}�U�[���o�������m�̋A���d�����͖̂��炩���B����ɂ��܂��āA�}�U�[�͂��̐l���ސ_�̖����̈��ɕ킢�]���Ă����̂��낤�B�����̐_�̈����A�C�G�X�̈����A�}�U�[�̂���{�������B
9.�@�}�U�[�́u�����킩���Ă��Ȃ��v�̈ꌾ�Ɏ����X�������B���ɍ��������Ȃ��M������Ă��A����͐�����_�ɂ��A�����Ă���אl�ɂ��A���͏o����Ă��Ȃ��Ȍ��t�ł���B����͑��l���Ƃł͂Ȃ��B�q�t�̎��́A�����Ō�錾�t�̍���ɁA���͒N���̗אl�Ȃ̂��Ǝ������g�ɑ���₢��Y���킯�ɂ����Ȃ��B�q�t����������邱�Ƃ́A�N���̗אl�Ƃ��ĕ��ނ��Ƃƕ\����̂̉c�݂�����B�����̎��̒�q�Ƃ��Ă̎p���A�����d�Ō�錾�t�̔w��Ɍ�炸�Ƃ������ƌ����Ă��ǂ��B�}�U�[�ɗ����߂��Č����A����̋A���𐽎��ɒS���Ȃ���A�����ɁA�l�Ԃ̍��o���l�X�Ȋu�Ă��z���Ă������ɕ킢�A���̈����x���Ƃ��ĕ������Ƃ����L���X�g�҂������ɂ����B���̃}�U�[�̊፷���̐�ɂ́A���������Ă����̂��낤�B�_�̖����̈��ɉ������C�G�X�����g�̕��݂��������͂����B��