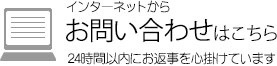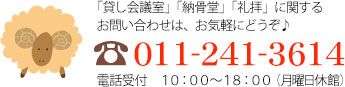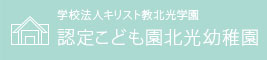札幌 納骨堂 札幌市中央区 貸し会議室 納骨堂/クリプト北光
日本基督教団 札幌北光教会 日曜礼拝 木曜礼拝 牧師/指方信平、指方愛子


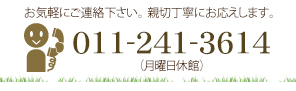
>札幌北光教会/トップ >牧師紹介・説教 >神の訪れる時
- テーマ
- 「神の訪れる時」
- 更新日:2025年4月21日
- 2025年4月13日 棕櫚の主日(受難節 第6主日) 説教要旨
ルカによる福音書 19章28節〜44節 - 牧師:指方 信平
■神の訪れに信仰の時計を合わせる
「神が訪れてくださる時」に自分の信仰の“時計”を合わせるという作業は大切です。これを放置すれば、必ず狂いが生じ、やがて自分の時だけが中心になり、神の訪れを見過ごすことになるでしょう。その意味で日曜日の礼拝は、信仰の時計の針を神に合わせる、欠かせない作業です。
■イエスの涙
イエスは、都エルサレムを眺めながら、泣いて言われました。「もし、この日にお前も平和への道をわきまえていたなら‥‥しかし今は、それがお前には見えない。やがて時が来て、敵が周りに堡塁を築き、お前を取り巻いて四方から攻め寄せ、お前とそこにいるお前の子らを地に叩きつけ、お前の中の石を残らず崩してしまうだろう。それは、神の訪れてくださる時をわきまえなかったからである。」
紀元70年、エルサレムはローマ帝国によって街も神殿も破壊し尽くされました。なぜ、そのような破滅に至ってしまったのか、ルカ福音書は、その原因を人々が「平和への道を弁えていなかったこと」「神の訪れてくださる時を弁えなかったこと」にあったと受け止め、そのことをイエスの発言として語っています。また、直後の箇所には、「わたしの家は祈りの家でなければならない。ところが、あなたたちはそれを強盗の巣にした」とのイエスの発言が記されていますが、ここにもエルサレム滅亡の原因が見つめられています。
エルサレムは、平和と繁栄の陰で人間の強欲と打算、傲慢と貪りで溢れていた。祭儀は形骸化し、民の心は神から遠く離れてしまっていた。神を前に自らを悔いて質すこともなく、ひたすら自分の時を中心にしていた。そこでは神が愛し造られた命が抑圧され、軽んじられていた。
イエスは、ご自分が裁かれ、荊の冠をかぶらされた時に悲しくて泣いたのではなく、人間のこのような現実に対してこそ泣いたのです。神があなたたちを訪れ、何度も呼びかけ、扉を叩いておられたのに、あなたたちは、聴く耳を持たず、立ち返ろうとせず、自ら破滅へと向かって言った。 しかし、当の本人たちは何も感じていないのです。大きな乖離がそこにはあります。
■「……」を想う
ルカによる福音書は、これを読んでいる私たちにも問いかけています。「主イエスが、あなたのために涙を流しておられることを忘れていないか?」と。私たちは自分のことで悲しんだり、あるいは人を傷つけ悲しませたりすることはあって、主を悲しませてしまっているということを、どれだけ自覚しているでしょうか。
「もしこの日に、お前も平和への道をわきまえていたなら……、しかし、今はそれがお前には見えない」。エルサレムを眺めて涙を流されたイエスの眼差しは、今日、私たちにも向けられています。この「……」には含みがあるように思います。主イエスの私たちへの眼差し、思いを感じ取りたいと思います。私たちが自分の時だけを中心に生き、神と隣人とをすっかり見失ってしまっているならば、また神がどのように私たちを訪れておられるかをわきまえずに、その時を見過ごしてしまっているならば、そのことに涙を流し嘆いているのです。しかし、この「……」には、イエスの嘆き悲しみだけでなく、私たちに対する「見えるようになれ!」という切なる願いも含められているのではないでしょうか。今は見えていないこの目が癒され、神と隣人とを見つめ、主が求めておられる平和への道を歩むことが切に願われているのです。
■十字架、神の愛の訪れ
神は、「何も弁えないお前は、もうどうしようもない」と言われ、完全に諦め、わたしたちを罪の内に死に、滅ぶままにされた方ではありません。神は、イエス・キリストの十字架の死をもって、私たちに対する愛と赦しを決断された。これは全く意外なことです。神は、愛することによって神であられる方です。「それでもお前はわたしにとってなくてはならぬ存在なのだ」と、御子キリストの死をもって、わたしたちを罪と死の縄目から解放し、御自身のものとして取り戻し、新たに生かしてくださいました。
人間は、その時何も知りませんでした。神の愛と赦しの訪れに何も気づかず、勝ち誇ったかのようにイエスを十字架の上に挙げたのです。しかし、その時、キリストはこう祈られました。「父よ、彼らをおゆるし下さい。自分が何をしているのか知らないのです」(ルカ23:34)。ここにわたしたちのまことの赦しがあり、そして癒しがあります。
■「主がお入り用なのです」
この十字架の出来事を通して、私たちは自分が神によってそれでも愛され、どこまでも愛され、必要なものとされてあることを知る時に、本当に悔い改めをもって神との交わりに生きるものとされるのです。私たちは、どのようにして神の訪れてくださる時を知り、交わることができるのでしょうか。次の言葉に答えがあると思います。「はっきり言っておく。わたしの兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたのは、わたしにしてくれたことなのである」(マタイ25:40)。
イエスは、ろばの子に乗ってエルサレムへと進んでいかれました。この子ろばは、まだ誰も乗せたことのない子どもでした(30節)。小さく何の役にも立たないかのような子ロバ、しかしこの子ロバこそ、主イエスに必要とされ、繋がれていた縄を解かれ、用いられました。ここに私たち自身の姿を重ね合わせたいと思います。主がこの私を見出し、必要とし、この私を罪と死の縄目から解き放ち、今日、この私をも用いて遣わされるのです。「主がお入り用なのです」、この呼びかけに応えて進みだしていくものでありたい。
⇒ 前のページに戻る