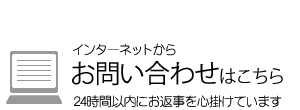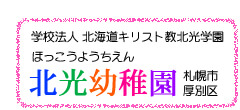札幌 納骨堂 札幌市中央区 貸し会議室 納骨堂/クリプト北光
日本基督教団 札幌北光教会 日曜礼拝 木曜礼拝 牧師/指方信平、指方愛子



>札幌北光教会/トップ >牧師紹介・説教 >黙するイエス
- テーマ
- 「黙するイエス」
- 更新日:2023年3月20日
- 2023年3月12日 受難節 第3主日 説教要旨
マタイによる福音書 27章15節〜31節 - 牧師:指方 信平
■沈黙するイエス
総督ピラトは、ユダヤ教の長老や祭司長たちのイエスに対する憎悪の原因が「ねたみ」であって、イエス本人には十字架に処される罪などないと分かっていました。そこでピラトはイエス釈放のために、札付きの悪人と評判のバラバ・イエスを民衆に提示し、どちらの恩赦が相応しいか選択させようとしました。ところがこの思惑は外れました。祭司長や長老たちが群衆を扇動し、バラバの釈放とイエスの処刑を要求させたのです。ピラトは、なお食い下がって尋ねました。23節「いったい(イエスが)どんな悪事を働いたというのか」。主イエス本人は、この場面で沈黙したまま何一つ弁明しません。まるでピラトが、イエスに代わって弁明しているかのようです。
■責任放棄
イエスを釈放すべきと考えていたピラトは、総督としての自らの地位を保つために、群衆の要求に臆しました。群衆によって「ピラトはローマの反逆者イエスを擁護した」などと吹聴されることを恐れたのではないでしょうか。ピラトは、自分自身に及ぶリスクを考えた時、たとえイエスへの訴えが不当であるとしても、強く打って出ることはできませんでした。そして、とうとうピラトは群衆の前で水で手を洗って、こう宣言したのです。「この人の血について、わたしには責任がない。お前たちの問題だ」。彼は公正な裁きを放棄し、自分の一切関知しない問題、ユダヤ人同士の問題として責任を逃れようとしました。群衆は「その血の責任は、我々と子孫にある!」(25節)と合唱しましたが、実際のところ、「我々と子孫」とは具体的に誰のことなのか、責任の所在は曖昧であって、所詮は無責任な言葉と言わざるを得ないでしょう。
■このすべてを導く神
ですが、ここで注目すべきなのは、果たして誰に責任があるのかということではありません。終始一貫して沈黙しているイエスこの方です。ここで主イエスはご自分の「血の責任」を誰にも問うていないということ、そこに注目したい。ご自分を陥れる人間の悪意、自己保身のために一人の命を奪おうとする野心、卑怯、そのような現実を追及して裁いたり、自らの無実を訴えたり、減刑を要求したりといったことは一切ないのです。着物をはぎ取られ、侮辱のしるしである赤い外套、茨の冠、葦の棒を身に着けらせられても。この場で一人何も語らず、沈黙を貫く主イエスの姿、ここに明確な答えがあります。すなわち、本来、ここで裁かれるべき人間の罪を、主イエスが裁かれて下さっている、引き受けてくださっているのだということを。
民衆がイエスの処刑を要求し、ピラトが責任を放棄する形で十字架を決定した。人間の思惑、自己保身と無責任が物事をすべて決定づけているように見えて、しかし、そこですべてを本当に導いているのは、ただ神であるのだということが語られているのです。神の御心は、イエスを裁きと苦痛から救い出してやるということではありませんでした。どこまでも自分本位で的外れな世の民を、それでも愛し、担うという神の決意がここにはあります。
■生きよ!
バラバにとってまさかの命拾い。それは彼自身が懇願したことではありませんでした。「イエス」という自分と同じ名の男のおかげで、思いがけず釈放されることになったのです。罪なきイエスが死に定められた引き換えに、本来死ぬはずだったバラバが解放された。バラバの死をイエスが死なれた。その大いなる交換の出来事を描きながら、福音書は「これはあなたの出来事に他ならない」と語っています。「主があなた自身を死んで下さったのだ、そのようにしてあなたを新たに生かそうする主がおられるのだ」と。
「あなたは生きよ!」「互いに神の子として生きよ!」「どうしてお前たちは死んで良いだろうか!」(エゼキエル18:31)という主の切なる命令が、沈黙するイエスにおいて告げられているのです。主は、わたしたちにイエスの血の責任を問うておられません。ただ、あなたが愛され赦された自分を生きていくものとなることが願われているのです。「わたしには責任がない」「わたしには関係がない」「自分は知らない」そう頑なに弁解すること、そうやって他者に対し傍観者の立場に位置し、目を背けること、あるいは無知であり続けることではなく、「あなたは、目を覚まして、生きよ」というのです。「あなたはそのことに無関係なのではない、関係大ありなのだ、そのことに無知であってはならない、目を背けてはならない、その現実の只中にわたしはある」と言われるのです。
人間の憎しみ、ねたみ、保身、企て、それらが騒がしく、全く収まる気配のない世の中です。私たち自身の心も、そのようにして騒ぎ続けているかもしれません。この喧騒の只中で黙って立ち続け、「あなたの生きるべき命を生きよ」と告げる主がおられるということを想うところから、わたしたちは、自分の語るべき言葉を語り、なすべき業をなしていくものでありたいと願います。
⇒ 前のページに戻る